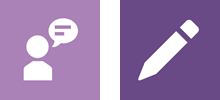TOEIC L&Rスコア300点台から世界の研究現場へ――TOEIC Testsと二人三脚で拓けた道
IIBC AWARD OF EXCELLENCE※を受賞された方にお話を伺うインタビューシリーズ。今回は、大学進学後、TOEIC L&Rスコア300点台から985点(リスニング495点、リーディング490点)までスコアを伸ばし、TOEIC S&Wでもスピーキング180点、ライティング200点を取得した内堀友加里さんです。現在はカナダのブリティッシュコロンビア大学で物理学の研究をされています。
※TOEIC TestsはTOEIC Listening & Reading Test(TOEIC L&R)、TOEIC Speaking & Writing Tests(TOEIC S&W)の総称です。
※ IIBC AWARD OF EXCELLENCE(IIBC AWARD)は、毎年1月~12月までに英語で「聞く」「読む」「話す」「書く」の4技能を測定するTOEIC L&R・TOEIC S&W・TOEIC Speakingで基準のスコアを取得した方を表彰する制度です。

内堀 友加里さん/ブリティッシュコロンビア大学
(UBC Department of Physics and Astronomy)
2024年IIBC AWARD OF EXCELLENCE受賞者
TOEIC Testsとの出会いであきらめかけた留学の道が拓けた
もともと英語は得意でしたか?
父が海外出張の多い仕事をしていたため、海外は身近に感じていたものの、ほとんど英語に触れることなく育ちました。中学からの科目としての英語は正直なところ苦手で、高校時代は習熟度別では最下位のクラス、大学入学時のTOEIC L&Rスコアは300点台でした。
大学時代、「父のように世界で活躍したい」という思いから留学を志しましたが、何をどう学べばいいのかわからない、まさに英語学習の迷子でした。周囲からも「留学はあきらめたほうがいい」と言われていました。
実際、TOEIC Tests以外の英語能力評価試験では思うような結果が出なかったため、留学をあきらめたこともあります。ところが、大学でTOEIC L&RのIPテスト(団体特別受験制度)を受ける機会があり、続けていくと回を重ねるごとに少しずつスコアが上がっていったのです。これが、私の英語学習の道筋を作ってくれました。
TOEIC Testsの魅力は、合否ではなく、勉強したことがスコアに反映されるところだと思います。「これなら私でも続けられるかもしれない」と思えたことで、学習への意欲も高まりました。
具体的な目標スコアは設定されていましたか?
目標を達成できないと落ち込んでしまうタイプなので、具体的なスコアは設定せず、「前回より少しでも上がれば十分」と考えることで、前向きに学び続けられました。
真剣に勉強し始めてから2年ほどで、TOEIC L&Rのスコアを925点(リスニング480点、リーディング445点)まで伸ばすことができました。外国語学科や国際系、経済・法学など英語を活用する専攻ではなかったものの、スコアの伸び率が学内でトップクラスでした。後にこのことを大学の紹介パンフレットで知ったときは、とても誇らしかったです。TOEIC Testsと二人三脚のように取り組んだ成果だと感じています。
自分に合った工夫で、TOEIC L&Rのスコアを伸ばす楽しさに気づく
TOEIC L&Rについては、どのような学習に取り組まれましたか?
最も力を入れたのは単語です。英単語には、「相性の良し悪し」があるように思います。一度見ただけで覚えられる単語もあれば、何度書いてもすぐに忘れてしまう単語もあります。私はまず単語帳を眺め、すでに覚えている単語を黒く塗りつぶしていきました。すると、自然と残った単語のなかから次に相性の良い単語に目が向きます。
そうして、実際に使えるようになったと感じたらまた塗りつぶす、という方法を繰り返しました。逆にどうしても覚えられない単語にはキラキラシールを貼って目立たせましたが、無理に暗記しようとはしませんでした。
この方法は効率よく語彙力を伸ばせるだけでなく、黒く塗った単語が増えていくことで、パズルのピースが埋まるような達成感も得られました。無造作に塗りつぶされた単語帳に、周囲はよく驚いていましたが、むしろそれを楽しんでいました。
TOEIC L&Rを軸にした英語学習は、どのように英語力向上に貢献しましたか?
TOEIC L&Rでは、文法的に正しく洗練された英語表現に数多く触れることができたため、英語力が着実に向上しました。さらに問題を解く過程はパズルのようで、楽しみながら論理的思考力も養えました。これは英語だけでなく、日本語での表現力まで高める結果につながったと実感しています。
苦手なスピーキングは実践と挑戦の積み重ねでスコアアップ
TOEIC S&Wを初めて受験されたきっかけは?
TOEIC S&Wに取り組み始めたのは、留学前、IPテストが大学で初めて実施されたタイミングです。「せっかくなら力試しをしてみよう」と思い、軽い気持ちで受験を決めました。初めての結果は、スピーキング130点、ライティング190点でした。
学習を進める上で、特に苦戦されたことや工夫されたことを教えてください。
最も苦労したのはスピーキングでした。30秒の準備時間の後に即座に答える形式が苦手で、何度も練習を重ねました。「独り言練習」を徹底し、ライティングで意識するような起承転結といった展開をスピーキングの練習にも応用するなど、自分に合った工夫を地道に続けました。
一方、ライティングでは数日に1問のペースで300語以上の長文問題に取り組み、延べ100問ほど解きました。こうした積み重ねがスコアアップにつながったのだと思います。
留学後「もう一度、自分の英語力を客観的に測りたい」と考えて、再びTOEIC S&Wを受験しました。日本でのキャリアも視野に入れていたため、実績として英語力を示せるスコアの必要性も感じていました。
この頃には、英語圏での生活がそのままライティングの実践となっていました。実際、オンラインショッピングで注文した商品が届かないために送った問い合わせメールが、TOEIC S&Wのライティング問題に酷似していて驚いたこともあります。
一方のスピーキングについては、日常生活での英会話には問題ありませんでしたが、即興スピーチに苦手意識がありました。そこで、「挑戦するならIIBC AWARDを目指そう」と決め、真正面から取り組みました。スピーチの構造を改めて学び直し、「序論→理由→詳細→結論」という型を頭に叩き込むことで、短時間でも論理的に話す力を養いました。
結果として、スピーキングは180点、ライティングは200点を獲得。長年の課題だったスピーキングに真剣に向き合ったことが、IIBC AWARD受賞という成果につながったのだと思っています。
モチベーションを保つ工夫は「無理なく続ける」の習慣化
日々の学習で、意識されていたモチベーション維持の工夫はありますか?
英語学習を長く続けるには、自分が楽しめる方法を見つけることが何より大切だと思っています。私は「自分のペースで無理なく続けられること」を意識していました。時間を決めて義務のように取り組むと、かえってやる気を失ってしまうことがあったため、机には常に英語の教材を開きっぱなしにしており、「勉強したいときに勉強する」というスタイルを大切にしていました。
自分の気分や集中力に合わせて学習することで、無理なく継続でき、英語学習が自然と習慣化されました。小さな達成感や「できるようになった」という実感を積み重ねることも心がけてきました。そうした工夫が、学びを苦痛にしない大きな要因となり、結果としてモチベーションの維持にもつながっていたと感じています。
TOEIC Testsの定期的な受験もモチベーション維持につながりましたか?
TOEIC Testsは、私にとって英語学習の指針でした。基準が明確で、努力がスコアに反映されるため、成果の確認もしやすく、学習の進捗を把握する上でも大きな助けになっていたと感じています。留学前は、大学で実施されるIPテストを半年に一度受験できる機会があり、自分の英語力を客観的に確認するためにも、毎回欠かさず受験していました。
もちろん、学習の過程では壁にぶつかることもありました。特に初期のころはリスニングの聞き取りに苦手意識があり、なかなか思うように理解できず苦労しました。そのような時期にはシャドーイングを地道に続けつつ、比較的成果が見えやすい単語学習にも力を入れることで、気持ちの面でも支えにしていました。すぐに成長を実感できる学習法を取り入れることで、停滞期を前向きに乗り越えることができたように思います。
英語学習10年の節目に届いた、IIBC AWARD OF EXCELLENCE受賞
IIBC AWARDを受賞したときのお気持ちを教えてください。
TOEIC Tests をきっかけに英語を学び始めてから、約10年になります。そんな節目のタイミングにIIBC AWARDを受賞できたことは、まるで英語学習の原点に立ち返るような感覚でした。古巣に温かく祝福されたような気持ちです。この受賞によって、自分の英語学習が客観的に評価されたと感じられ、大きな自信につながりました。
「IIBC AWARDを受賞してインタビューを受ける」ということも、ひそかな目標でした。TOEIC Testsにはとても助けられたので、感謝の気持ちを何らかのかたちで伝えたい――そんな思いがありました。そして今、英語を学ぶことで広がる可能性を、かつての私のように悩んでいる人たちに届けられたらという願いがあります。
英語を学ぶことでどのような可能性が広がりましたか?
私にとって、英語を学ぶことは「想像もしなかった未来」を拓く鍵でした。夢だった留学が実現し、海外の大学院に進学できただけでなく、海外の研究所で有給インターンを経験するなど、次々と新たな道が拓いていきました。
現在はカナダのブリティッシュコロンビア大学にて、カナダ水素強度マッピング実験(Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment: CHIME)のメンバーとして、宇宙の膨張や暗黒エネルギーの解明に取り組んでいます。世界初の成果を目指し、約60億年前に放たれた光の解析などを進めています。CHIMEは、世界でも有数のユニークな望遠鏡で、日本には存在しない設計を持ち、ブリティッシュコロンビア大学近郊に設置されています。
北米各地の複数の研究機関が参加し、毎週のオンラインミーティングでは英語による活発な議論が行われます。私個人も、招待講演を含め、日本・台湾・北米でCHIMEを代表して講演を行い、カンファレンスに出席する機会にも恵まれています。英語は、文字どおり私の世界を広げてくれました。
成長の証しを未来へ――IIBC AWARDが拓くキャリアの可能性
この受賞は今後の学びやキャリアに、どのような意味を持つと思いますか?
IIBC AWARDは、私にとって英語学習における「さらなる挑戦へのきっかけ」です。特に苦手だったスピーキング分野で成果を出せたことは、長年の努力の結実となりました。この受賞は今後の進路を決めるための活動のなかでも、努力を重ねて成果に結びつける姿勢そのものとして評価される場面がありました。
この受賞を、今後のキャリアにどう活用していきたいと考えていますか?
英語力を証明する客観的な指標として、IIBC AWARDは大きな強みになります。すでに履歴書に記載しており、インタビュー掲載URLも応募書類に添える予定です。単なるスコアでは伝わらない、継続的な学びと挑戦の軌跡を示す材料として、キャリア形成の大きな支えになると考えています。
広がる研究と語学力――尽きない学びのその先へ
今後の英語学習における目標は?
私は英語で学んだことは英語として、日本語で学んだことは日本語として定着する傾向があります。そのため、両言語を母語のように自在に切り替えられる感覚を持ち、日本語でも英語でもあらゆる内容の議論ができるようになることが、現在の最大の目標です。
TOEIC Testsでは、現在、リスニング・リーディング・ライティングで最高点を取得していますが、スピーキングはまだ達していません。4技能すべてで最高点を取ることが、英語学習の一つの到達点としての目標です。
研究活動やキャリアへの展望は?
将来的には、日本または海外で研究を継続しつつ、国際的な学術交流に貢献したいと考えています。特に日本では、専門的議論で英語が必ずしも主流とは言えない現状もあり、自分の語学力を活かして学術の国際化を後押ししたいです。
TOEIC Testsは未来への道しるべ
最後にこれからIIBC AWARDの受賞を目指す方や英語学習を頑張ろうと思っている方へのメッセージをお願いいたします。
英語が苦手で、留学を志しても何から始めればいいのかすらわからず、留学をあきらめかけていたときに出会ったTOEIC Testsは、私にとって「英語学習の道しるべ」でした。努力がスコアに反映される明確な基準があることで、成果が見えやすく、目標を持って取り組めるようになったからです。シャドーイングを続け、スピーキングに挑戦し、英語の世界が少しずつ広がっていきました。
その結果、長年の夢だった留学が実現し、今の私へと導いてくれました。TOEIC Testsから始まった学習が私の人生の可能性を大きく広げてくれたのです。
英語学習は、時に困難で、成長が感じづらいときもあります。しかし、TOEIC Testsはその道のりを「可視化」してくれます。学習者の努力を記録し、次の目標を教えてくれる羅針盤です。また、電卓が普及しても基礎的な計算力が欠かせないように、翻訳AIの時代でも「その場で自然に伝える力」が求められます。英語学習は、その力を育て、人生の選択肢とチャンスを確実に広げてくれるのです。
TOEIC Testsはただの試験ではありません。それは「人生を前に進めるためのツール」です。あきらめなければ、英語力は必ず伸びます。そしてその力は、想像以上の未来をあなたに届けてくれます。どうか、自分だけの道を切り拓いていってください。心から、あなたの挑戦を応援しています。
おすすめ記事

- 2024年受賞者
川邉 峻さん
サンワ産業株式会社
2025.10.14
TOEIC Testsを活用してキャリアを切り拓き、“伝える力”を磨く

- 2024年受賞者
内堀 友加里さん
ブリティッシュコロンビア大学
(UBC Department of Physics and Astronomy)
2025.10.03
TOEIC L&Rスコア300点台から世界の研究現場へ――TOEIC Testsと二人三脚で拓けた道

- 2024年受賞者
石川昇太朗さん
立命館大学 文学部 人文学科 4年生
2025.09.22
英語を教える夢に向け、TOEIC Testsで英語4技能に磨きをかける

- 2024年受賞者
西本大晟さん
立教池袋高等学校 3年生
2025.09.11
目指すは「使える英語」で世界とつながること——学び続ける高校生の挑戦